近畿大学奈良病院整形外科
専門研修プログラム

1. 近畿大学奈良病院整形外科専門研修プログラムの理念
奈良県西和医療圏における唯一の大学病院である当院では
- 1)患者本位の開かれた病院として、安全で質の高い医療を提供する
- 2)特定機能病院として、医学医療の進歩に関与し社会に貢献する
- 3)教育病院として、人に愛され信頼され尊敬される医療人を育成する
- 4)働きがいのある病院として、環境整備に努力する

1) 豊富な知識と実践的な技術
整形外科医師として全ての運動器疾患に関する知識を系統的に理解し、新たに生み出される知見を吸収し続ける態度を身につける。そして、豊富な症例数に基づいた研修により、運動器全般に関して的確な診断能力を身につけ、適切な保存療法、リハビリテーションを運動器全般に関して的確な診断能力を身につけ、適切な保存療法、リハビリテーションを実践する。さらに、基本手技から最先端技術までを網羅した手術治療を経験することで、運実践する。さらに、基本手技から最先端技術までを網羅した手術治療を経験することで、運動器疾患に関する良質かつ安全な医療を実践する。動器疾患に関する良質かつ安全な医療を実践する。
2) 診療における探究心の涵養
運動器疾患の診断および治療における臨床的問題点を見出して解明しようとする探究心を持つ。そして、リサーチクエスチョンを 正しく設定し、その解答を科学的に導き出し、論理的に正しくまとめ、公表する能力を身につける。
3) 人格の陶冶
豊かな人間性と高い倫理観に基づき、整形外科医師として暖かな心をもって患者に接し、国民の運動器の健全な発育と健康維持に貢献する。また、 医療関連法規を理解し、安全で適正な医療を提供する医師として活躍する。
近畿大学奈良病院整形外科専門研修プログラムにおいては、指導医が専攻医の教育および指導にあたりますが、専攻医自身が主体的に学ぶ姿勢をもつことも重要であると考えます。皆さんは自己研鑽に努め自己の知識と技量を高めると共に、積極的に臨床研究や医療技術開発に関わり、効率的で良質の患者満足度の高い医療提供者となることが期待されます。
また、チーム医療のー員として行動し、患者や医療関係者とのコミュニケーション能力を磨くことによって周囲から信頼され、愛される医師となることも重要です。本研修プログラムの終了後には、皆さんは運動器疾患に関する良質かつ安全で心のこもった医療提供者となるとともに、将来の医療の発展に貢献できる整形外科専門医となることが期待されます。
専攻医の皆さんが本プログラムを通じて有能な整形外科専門医として育ち、充実した医師人生を送ることができるように最大限のサポートをさせていただきます。
2. 近畿大学奈良病院整形外科専門研修の特徴
本研修プログラムでは、基幹施設(近畿大学奈良病院)および連携施設全体において関節外科、脊椎外科、手外科、骨軟部腫瘍、外傷、リウマチ、スポーツ医学、小児整形外科などの専門性の高い診療を早くから経験することができます。
本研修プログラムは大きく分けて、①一般研修コース、②大学病院コース、③大学院コース、の3パターンがあります。
①の一般研修コースでは基幹施設である近畿大学奈良病院、近畿大学病院での研修期間は6ヶ月以上としますが(必須条件です、それ以外の研修期間は連携施設でプログラムを組みます。
②の大学病院コースでは大学本院と近畿大学奈良病院で2年間を研修し、残りの1年9ヶ月は連携研修病院で研修を行ないます。
③の大学院コースでは、研修開始と同時に社会人大学院に入学し、大学及び近隣連携施設に勤務しながら医学研究に従事し、研修プログラム修了と同時に学位を取得することが可能です。①および②のコース修了の後に大学院に入学し、課程博士学位を取得することももちろん可能です。
研修プログラム終了後の進路としては、①連携病院のスタッフとして勤務する、②近畿大学奈良病院のスタッフ(助教)として勤務し、整形外科サブスペシャルティ領域の臨床修練を行なう、③研修プログラム終了後に大学院に入学し、学位を取得するための基礎研究に従事する、の3つがあります。さらに、国内外の他施設へ留学し、さらに研究や診療能力の幅を深める選択肢もあります。大学院に入学せず医学博士号取得を希望するものには、論文博士学位取得の機会もあります。
研修プログラム終了後にサブスペシャルティ領域の研修に直接進む場合には、希望する領域の専門診療班に所属し、近畿大学奈良病院ならびに連携施設において専門領域の研修を行います。
① 近畿大学奈良病院整形外科
奈良病院整形外科は1999年に奈良県生駒市の自然豊かな丘陵に開設された比較的新しい施設です。2019年4月に戸川大輔が准教授として着任、2020年には臨床教授に就任いたしました。スタッフ6名で脊椎外科、関節外科、関節リウマチ診療、運動器外傷・救急に熱心に取り組んでいます。手術症例数も飛躍的に増加し、大学本院と連携を取りつつも本院とは一味違う地域の基幹病院として活動しており、奈良病院での後期研修は整形外科 commondiseases を学ぶ格好の場となっています。また大学本院とのモーニングレクチャーや定期的に開かれる臨床研究報告会を通じて、最新の医療知識に接することができます。
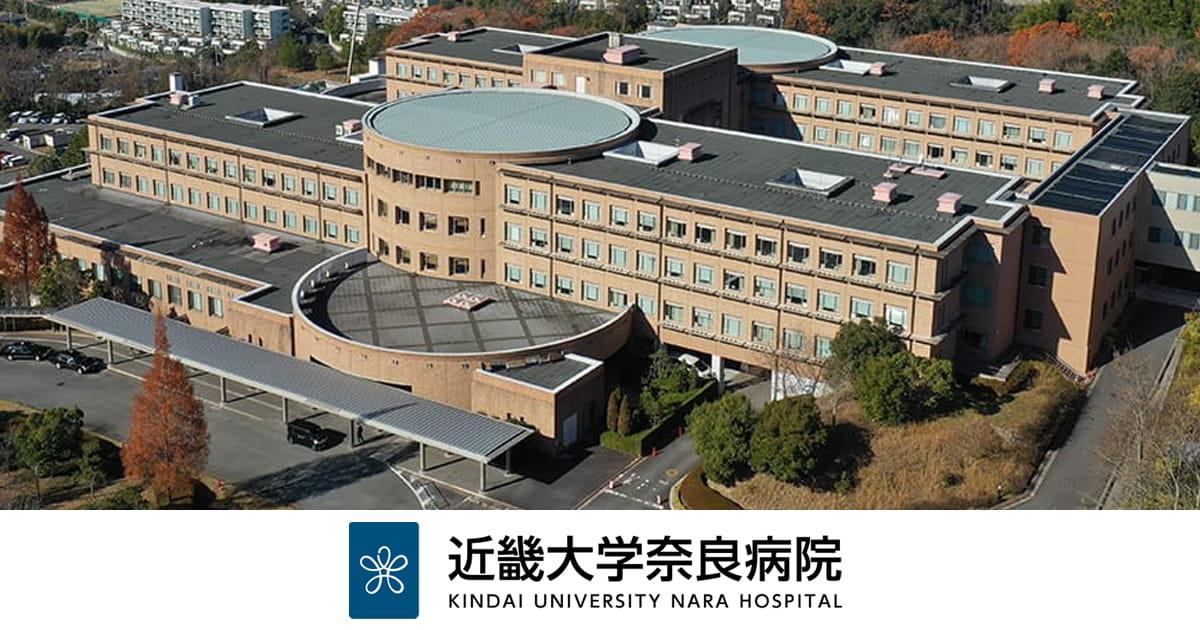
② 近畿大学整形外科学教室
近畿大学整形外科学教室は1974年に開講し、2024年に開講50周年を迎える歴史ある整形外科教室です。初代山室隆夫教授、2代田中清介教授、3代濵西千秋教授、4代赤木將男教授と続き、2023年からは後藤公志教授が教室を主宰しています。関節班、脊椎班、上肢班、腫瘍班、外傷班の5つの診療班からなり、その他、人工関節センターと運動器外傷センターを併設して専門医を配置しています。そのため近畿大学病院における研修では、それぞれの診療専門班に所属することによりサブスペシャルティにおけるレベルの高い研修を受けることができ、臨床研究に対する関わりを深く持つことができます。

大学病院本院では各臨床班の論文抄読会を通じて最新の医療知識や研究動向を知ることができます。年に2回当番として当たる月曜日朝のモーニングレクチャーでは、教授以下医局員全員が自分の興味あるテーマを取り上げて講演を行ない、専門領域を超えてお互いに学び合う機会を設けています。
また、近畿大学医学部および大学病院は現在の大阪狭山市から堺市泉ヶ丘へ新築移転し(2025年予定)、駅直結型の最新医療設備を備えた病院へと生まれ変わります。大阪市内や関西空港への交通アクセスも格段に改善され、南大阪地域で唯一の大学病院として今後の飛躍的な発展が期待され、恵まれた就労環境の中での専門研修が可能となります。
③ 専門研修連携施設
本専門研修プログラムでは、地域医療の拠点となっている施設(地域中核病院)として市立岸和田市民病院、阪南市民病院、天理よろづ相談所病院、耳原総合病院、くしもと町立病院、都市型総合病院である宝生会PL病院、育和会記念病院があり、地域医療研修施設としてさくら会病院、樫本病院、南河内おか病院、咲花病院などがあります。
いずれの連携施設も豊富な症例数を有しており、本研修プログラムにより3年9ヶ月間で400例以上の手術執刀(術者)経験を十分に積むことができます。また執刀した症例は原則として主治医として担当することで、医師としての責任感を育み、患者やメディカルスタッフなどとの良好なコミュニケーション能力を育んでいきます。
3. 近畿大学奈良病院整形外科専門研修プログラムの目標
あらゆる運動器に関する科学的知識と高い社会的倫理観を備え、さらに、最新医学の知識と技能を修得できる幅広い基本的臨床能力(知識・技能・態度)が身についた整形外科専門医の育成を目標としています。具体的には以下のコアコンピテンシーの習得を目指します。
- 1) 患者や医療関係者とのコミュニケーション能力
- 2) 自律的に責務を果たし、信頼を得る(プロフェッショナリズム)
- 3) 診療記録の適確な記載
- 4) 医の倫理、医療安全等に配慮した、患者中心の医療の実践
- 5) 臨床的問題から基礎医学や臨床医学の知識や技術を修得する姿勢
- 6) チーム医療の一員としての行 動
- 7) 後進医師への教育、指導
4. 専門研修の方法
参照資料
整形外科専門研修プログラム整備基準付属資料(資料1~13)
(日本整形外科学会 HP)http://www.joa.or.jp/jp/edu/index.html
1ヶ月の研修を1単位とする単位制をとり、全カリキュラムを10の研修領域に分割し、基幹施設および連携施設をローテーションすることで、それぞれの領域で定められた修得単位数以上を修得し、3年9か月間で45単位を修得する修練プロセスで研修します。
本研修プログラムにおいては3年9か月間で手術手技を400例以上経験し、そのうち術者としては200例以上を経験します。尚、術者として経験すべき症例については、資料3整形外科専門研修カリキュラムに示した(A:それぞれについて最低5例以上経験すべき疾患、B:それぞれについて最低1例以上経験すべき疾患)疾患の中のものとします。術前・術後カンファレンスにおいて症例提示と手術報告をすることで、手技および手術の方法や注意点を深く理解し、整形外科的専門技能の習得を行います。指導医は上記の事柄について、責任を持って指導します。
日本整形外科学会学術集会時に教育研修講演(医療安全、感染管理、医療倫理、指導・教育、評価法に関する講演を含む)に参加します。また関連学会・研究会において日本整形外科学会が認定する教育研修会、各種研修セミナーで、国内外の標準的治療および先進的・研究的治療を学習します。特に本研修プログラムでは、近畿大学整形外科同門会が主催する夏期研究会(年1回4講演、4年間で24講演)、新年学術集会(年1回1講演、4年間で4講演、一般演題発表あり)および、整形外科金剛会(年1回2講演、4年間で8講演、一般演題発表あり)に参加することにより、他地域の整形外科指導者からの多領域にわたる最新知識の講義を受けると同時に、自ら発表する機会が設けられています。
特定機能病院である近畿大学奈良病院では年に5回程度の安全管理講習会、年に5回程度の院内感染対策講習会、年に3回程度の医療倫理講習会が開催されており、職員は安全管理・院内感染対策講習会を年に2回以上受講することが義務づけられています。このように、コアコンピテンシーの研修機会は十分医用意されています。
専攻医は医局内に各自の机と椅子、書棚が供与され、個別性のある学習環境が与えられます。各個人にはインターネットのLANあるいはWiFi接続環境が与えられています。そして、本プログラム基幹施設および連携施設の院内インターネット環境から医学中央雑誌やPubMedなどにアクセスし、基礎および臨床関連の多くの医学雑誌にアクセスし論文のfulltextをダウンロードすることができます。大学本院、奈良の2病院からは近畿大学電子ジャーナル検索ポータルに接続することができ、広範囲の学術雑誌にアクセスすることができます。
さらに、日本整形外科学会や関連学会が認定する教育講演受講、日本整形外科学会が作成する e Learning や Teaching file などを活用して、より広く、より深く学習することができます。また、日本整形外科学会作成の整形外科卒後研修用 DVD 等を利用することにより、診断・検査・治療等についての教育を受けることもできます。
本プログラムには、①一般研修コース、②大学病院コース、③大学院コース、の3パターンの研修方式が用意されていますが、①の場合には大学本院で半年~1年、②の場合には大学本院と奈良病院で1年ずつ、③の場合には大学本院で2年間の研修を受けて頂きます。大学病院では全ての領域の症例を数多く経験することが出来ます。以下に近畿大学奈良病院での研修の週間スケジュールと研修コースの例を示します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 8:00~8:30 | モーニングレクチャー | 手術カンファレンス | 研究カンファレンス 学会予演 |
||
| 8:30~9:00 | 教授回診 | ||||
| 9:00~17:00 | 外来・手術 | 外来・手術 | 外来・手術 | 外来・手術 | 外来・手術 |
| 16:00~16:30 | 脊椎回診 | ||||
| 16:30~17:00 | リハビリテーションカンファレンス |
| コース | プログラム | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目(9か月) |
| 1 | 一般研修コース1 | A | B | C | A/B/C |
| 2 | 一般研修コース2 | 大学本院 | A | B | C/奈良病院 |
| 3 | 一般研修コース3 | 奈良病院 | A | B | C/大学本院 |
| 4 | 大学病院コース1 | 大学本院 | 奈良病院 | A/B/C | 大学本院 |
| 5 | 大学病院コース2 | 奈良病院 | 大学本院 | A/B/C | 奈良病院 |
| 6 | 大学病院コース3 | 奈良病院 | 奈良病院 | A/B/C | 大学本院 |
| 7 | 大学院コース1 | 大学本院 | 奈良病院 | A/B/C | 大学本院 |
| 8 | 大学院コース2 | 奈良病院 | A/B/C | 大学本院 | 大学本院 |
| 9 | 大学院コース3 | 大学本院 | A/B/C/奈良 | 大学本院 | 大学本院 |
グループ A:近畿大学病院、奈良病院、市立岸和田市民病院、宝生会PL 病院、育和会記念病院、天理よろづ相談所病院、耳原総合病院
グループ B:さくら会病院、樫本病院、南河内おか病院、阪南市民病院
グループ C:くしもと町立病院、咲花病院、かわい病院
注)
1)「奈良病院」とは近畿大学奈良病院、「大学本院」とは近畿大学病院のこと
2)「A」とは、グループ A の病院より1病院を選択するとの意味
3)「A/B」とは、グループ A または B の病院から1病院を選択するとの意味
5. 研修の評価
① 形成的評価
1) フィードバックの方法とシステム
専攻医は、各研修領域終了時および研修施設移動時に日本整形外科学会が作成したカリキュラム成績表(資料7)の自己評価欄に行動目標毎の自己評価を行います。また指導医評価表(資料8)で指導体制、研修環境に対する評価を行います。指導医は、専攻医が行動目標の自己評価を終えた後にカリキュラム成績表(資料7)の指導医評価欄に専攻医の行動目標の達成度を評価します。尚、これらの評価は日本整形外科学会が作成した整形外科専門医管理システムからwebで入力します。指導医は抄読会や勉強会、カンファレンスの際に専攻医に対して教育的かつ建設的フィードバックを行います。
2) 指導医層のフィードバック法の学習(FD)
指導医は、日本整形外科学会が行う指導医講習会等を受講してフィードバック法を学習し、より良い専門医研修プログラムの作成に努めています。指導医講習会には、フィードバック法を学習するために「指導医のあり方、研修プログラムの立案(研修目標、研修方略及び研修評価の実施計画の作成)、専攻医、指導医及び研修プログラムの評価」などが組み込まれています。
② 総括的評価
1) 評価項目・基準と時期
専門専攻研修4年目の12月に研修期間中の研修目標達成度評価報告と経験症例数報告をもとに総合的評価を行い、専門的知識、専門的技能、医師としての倫理性、社会性などを習得したかどうかを判定します。
2) 評価の責任者
年次毎の評価は専門研修基幹施設や専門研修連携施設の専門研修指導医が行います。専門研修期間全体を通しての評価は、専門研修基幹施設の専門研修プログラム統括責任者が行います。
3) 修了判定のプロセス
研修基幹施設の整形外科専門研修プログラム管理委員会において、各専門研修連携施設の指導管理責任者を交えて修了判定を行います。
修了認定基準は、
- 修得すべき10領域分野での必要単位を取得すること(別添の専攻医獲得単位報告書(資料9)を提出)
- 行動目標のすべての必修項目について目標を達成していること
- 臨床医として十分な適性が備わっていること
- 研修期間中に日本整形外科学会が主催又は認定する教育研修会を受講し、所定の手続により30単位を修得していること
- 1回以上の学会発表、筆頭著者として1編以上の論文があること
4) 他職種評価
専攻医に対する評価判定に他職種(看護師、薬剤師、技師、事務員、等)の医療従事者の意見も加えて医師としての全体的な評価を行い専攻医評価表(資料10)に記入します。専攻医評価表には指導医名以外に医療従事者代表者名を記します。
6. 専門研修プログラムの施設群
専門研修基幹施設
近畿大学奈良病院整形外科(Ⅱ 型専門研修プログラム基幹施設)
専門研修連携施設
近畿大学奈良病院整形外科研修プログラムの施設群を構成する連携病院は以下の通りです。全て専門研修連携施設の認定基準を満たしています。
- 近畿大学病院(グループ A)(Ⅰ型専門研修プログラム基幹施設)
- 市立岸和田市民病院(グループ A)
- 天理よろづ相談所病院(グループ A)
- 宝生会 PL 病院(グループ A)
- 育和会記念病院(グループ A)
- 耳原総合病院(グループ A)
- さくら会病院(グループ B)
- 樫本病院(グループ B)
- 阪南市民病院(グループ B)
- くしもと町立病院(グループC)
- 咲花病院(グループC)
- かわい病院(グループC)
専門研修施設群の地理的範囲
近畿大学奈良病院整形外科専門研修プログラムの専門研修施設群は、奈良県西和医療圏、南大阪および大阪市内、和歌山県にあります。施設群の中には、地域中核病院が含まれています。
7. 専攻医の受け入れ数
各専攻医指導施設における専攻医総数の上限(4学年分)は、当該年度の指導医数×3となっています。各専門研修プログラムにおける専攻医受け入れ可能人数は、専門研修基幹施設および連携施設の受け入れ可能人数を合算したものです。またプログラム参加施設の合計の症例数で専攻医の数が規定され、プログラム全体での症例の合計数は、(年間新患数が500例、年間手術症例を40例)×専攻医数とされています。この基準に基づき、専門研修基幹施設である近畿大学奈良病院整形外科と専門研修連携施設全体の指導医数は48名、新患数は年間27,000以上、年間手術件数およそ6,200件と十分な指導医数と症例数を有しますが、質量ともに十分な指導を提供するために1年に4名を受入数とします。
8. 地域医療・地域連携への対応について
整形外科専門医制度は、地域の整形外科医療の整備と発展を念頭に置いています。地域医療研修病院における外来診療および二次救急医療に従事し、主として一般整形外科外傷の診断、治療、手術に関する研修を行います。また地域医療研修病院における近隣医療機関との病病連携、病診連携を経験・習得します。本研修プログラムでは、専門研修基幹施設である近畿大学奈良病院が所在する奈良県西和医療圏以外の地域医療研修病院に12ケ月(12単位)以上勤務することによりこれを行います。他県にある連携施設とは長年にわたって人事交流があります。これらの連携施設で研修することにより、別の地域における整形外科診療や病病連携、病診連携を経験することができます。
地域において指導の質を落とさないための方法として、地域医療研修病院の指導医には近畿大学整形外科同門会が主催する夏期研究会、新年学術集会、整形外科金剛会、南大阪運動器診療連携研究会への参加を義務付け、他地域の整形外科指導者が提供する広範囲の最新知識に関する講義を受けると同時に、自らが指導する専攻医の集談会あるいは学会への参加を必須としています。また研修関連施設の指導医は、自らが指導した専攻医の評価報告を行います。同時に、専攻医から研修プログラム管理委員会に提出された指導医評価表に基づいたフィードバックを受けることになります。
9. サブスペシャルティ領域との連続性
近畿大学奈良病院整形外科専門研修プログラムでは各指導医が脊椎・脊髄外科、関節外科、手外科、スポーツ整形外科、外傷、腫瘍外科、関節リウマチ等のサブスペシャルティを有しています。専攻医が興味を有し将来指向する各サブスペシャルティ領域については、指導医のサポートのもと、より深い研修を受けることができます。なお、専攻医によるサブスペシャルティ領域の症例経験や学会参加は強く推奨されます。
10. 整形外科研修の休止・中断、プログラム移動の条件
傷病、妊娠、出産、育児、その他やむを得ない理由がある場合の休止期間は合計6ヶ月間以内とします。限度を超えたときは、原則として少なくとも不足期間分を追加履修することになります。疾病の場合は診断書の、妊娠・出産の場合はそれを証明するものの添付が必要です。留学、診療実績のない大学院の期間は研修期間に組み入れることはできません(大学院での研究の傍ら一部の診療に従事し、カンファレンス・回診に出席することが望まれます)。また研修の休止期間が6ヶ月を超えた場合には、専門医取得のための専門医試験受験が1年間遅れる場合もあります。専門研修プログラムの移動に際しては、移動前・後のプログラム統括責任者及び整形外科領域の研修委員会の同意が必要です。
11. 専門研修プログラムを支える体制
① 専門研修プログラムの管理運営体制
基幹施設である近畿大学奈良病院においては、指導管理責任者(プログラム統括責任者を兼務)および指導医の協力により、また専門研修連携施設においては指導管理責任者および指導医の協力により専攻医の評価体制を整備します。専門研修プログラムの管理には添付した日本整形外科学会が作成した指導医評価表や専攻医評価表などを用いた双方向の評価システムにより、互いにフィードバックすることから研修プログラムの改善を行います。
上記の目的達成のために専門研修基幹施設に専門研修プログラムと専攻医を統括的に管理する整形外科専門研修プログラム管理委員会を置き、年に一度開催します。
② 労働環境、労働安全、勤務条件
労働環境、労働安全、勤務条件等は近畿大学奈良病院(専門研修基幹施設)や専門研修連携施設の病院規定に従います。
- 研修施設の責任者は専攻医のために適切な労働環境の整備に努めます
- 研修施設の責任者は専攻医の心身の健康維持に配慮します
- 過剰な時間外勤務を命じないようにします
- 施設の給与体系を明示し、3年9か月間の研修で専攻医間に大きな差が出ないよう配慮します
専攻医の勤務時間、休日、当直、給与などの勤務条件については、労働基準法を遵守し、各施設の労使協定に従います。さらに、専攻医の心身の健康維持への配慮、当直業務と夜間診療業務の区別とそれぞれに対応した適切な対価を支払うこと、バックアップ体制、適切な休養などについて、勤務開始の時点で説明を行います。
総括的評価を行う際、専攻医および指導医は専攻医指導施設に対する評価も行い、その内容は近畿大学病院整形外科専門研修管理委員会に報告されますが、そこには労働時間、当直回数、給与など、労働条件についての内容が含まれます。
12. 専門研修実績記録システム、マニュアル等について
① 研修実績および評価を記録し、蓄積するシステム
原則として日本整形外科学会が作成した整形外科専門医管理システム(作成中)を用いて整形外科専門研修カリキュラムの自己評価と指導医評価及び症例登録をweb入力で行います。日本整形外科学会非会員は、紙評価表を用います。
② 人間性などの評価の方法
指導医は別添の研修カリキュラム(資料3)「医師の法的義務と職業倫理」の項で医師としての適性を併せて指導し、整形外科専門医管理システムの専攻医評価表(資料10参照)を用いて入院患者・家族とのコミュニケーション、医療職スタッフとのコミュニケーション、全般的倫理観、責任感を評価します。
③ プログラム運用マニュアル・フォーマット等の整備
日本整形外科学会が作成した①整形外科専攻医研修マニュアル(資料13)、②整形外科指導医マニュアル(資料12)、③専攻医取得単位報告書(資料9)、④専攻医評価表(資料10)、⑤指導医評価表(資料8)、⑥カリキュラム成績表(資料7)を用います。③、④、⑤、⑥は整形外科専門医管理システムを用いてweb入力することが可能です。日本整形外科学会非会員の場合、紙評価表、報告書を用います。
④ 指導者研修計画(FD)の実施記録
指導医には日本整形外科学会が行う指導医講習会等を受講すると指導医に受講証明書が交付されます。指導医はその受講記録を整形外科専門研修プログラム管理委員会に提出し、同委員会はサイトビジットの時に提出できるようにします。受講記録は日本整形外科学会でも保存されます。
13. 専門研修プログラムの改善方法
① 専攻医による指導医および研修プログラムに対する評価
日本整形外科学会が作成した指導医評価表を用いて、各々のローテーション終了時(指導医交代時)毎に専攻医による指導医や研修プログラムの評価を行い研修プログラムの改善を継続的に行います。専攻医が指導医や研修プログラムに対する評価を行うことで不利益を被ることがないように、研修プログラム統括責任者が報告内容を匿名化して研修プログラム管理委員会に提出します。研修プログラム管理委員会では研修プログラムの改善に生かすようにするとともに指導医の教育能力の向上を支援します。
② 研修に対する監査(サイトビジット等)・調査への対応
研修プログラムに対する日本専門医機構など外部からの監査・調査に対して研修プログラム統括責任者および研修連携施設の指導管理責任者ならびに専門研修指導医及び専攻医は真摯に対応、プログラムの改良を行います。専門研修プログラム更新の際には、サイトビジットによる評価の結果と改良の方策について日本専門医機構の整形外科研修委員会に報告します。
14. 応募方法と病院見学について
① 応募資格
初期臨床研修修了見込みの者であること。
② 応募方法
毎年7月頃より研修プログラム説明会などを複数回行い、整形外科専攻医を募集します。翌年度のプログラムへの応募を希望する場合、下記連絡先宛に所定の形式の『近畿大学奈良病院整形外科専門研修プログラム応募申請書』および履歴書を提出してください。
申請書は
- (1)近畿大学奈良病院 後期臨床研修プログラムのプログラム科目>整形外科
(https://www.kindainara.com/bumon/kensyucenter/koukirinsho_program/)よりダウンロード - (2)近畿大学奈良病院整形外科医局に電話で問い合わせ(内線 3883)
- (3)近畿大学奈良病院整形外科医局に Eメールで問い合わせ
(naraseikei@med.kindai.ac.jp)
のいずれの方法でも入手可能です。原則として11月中に採否を決定して本人に文書で通知します。応募者および選考結果については12月の近畿大学奈良病院整形外科専門研修プログラム管理委員会において報告します。
③ 病院見学、研修プログラム説明会への参加
随時受け付けていますので、詳しくは下記連絡先あてにご連絡ください。
〒630-0293 奈良県生駒市乙田町1248番-1
近畿大学奈良病院整形外科
秘書:鎌田 央保(かまだみほ)
TEL:0723-77-0880(内線3883)