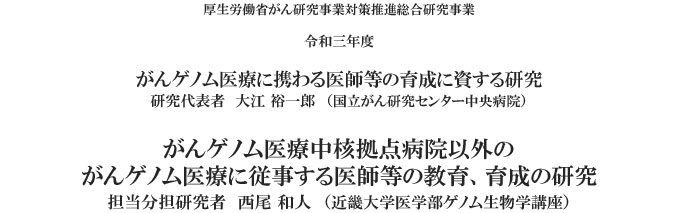
| 役割 | 氏名 | 所属 |
| 代表 | 大江 裕一郎 | 国立がん研究センター中央病院呼吸器内科 |
| 分担 | 西尾 和人 | 近畿大学医学部ゲノム生物学教室 |
| 分担 | 小山 隆文 | 国立がんセンター中央病院先端医療科 |
| 分担 | 高橋 秀明 | 国立がんセンター東病院肝胆膵内科 |
| 分担 | 浜本 康夫 | 慶應義塾大学医学部腫瘍センター |
| 分担 | 櫻井 晃洋 | 札幌医科大学医学部遺伝医学 |
| 分担 | 中谷 中 | 三重大学医学部附属病院中央検査部 |
| 分担 | 武田 真幸 | 奈良県立医科大学がんゲノム・腫瘍内科学講座 |
| 協力 | 林 秀幸 | 慶應義塾大学医学部腫瘍センター |
| 協力 | 天野 虎次 | 北海道大学大学院医学研究院内科系部門内科学分野腫瘍内科学教室 |
| 協力 | 奥川 喜永 | 三重大学医学部附属病院ゲノム医療部 |
| 協力 | 坂井 和子 | 近畿大学医学部ゲノム生物学教室 |
教育目標
がんゲノム医療中核拠点病院以外の拠点病院、連携病院等で、がんゲノム医療に従事する医師等が 備えるべき知識や資質等を習得し、がんゲノム医療を患者に提供することを目標とする。- ディプロマポリシー 一般目標を達成するに必要な講義およびアクティブ・ラーニングの研修を受講し、その学習効果が到達目標に達したことを事後評価で客観的に検証した上で、研修を修了することを目指す。
- GIO (一般目標) がんゲノム医療の実用化に必要な医療従事者として、遺伝子関連検査、患者・家族への伝え方、多職種との連携、意思決定支援等について必要な知識・態度・技術を習得する。
- SBO (到達目標) 1. Pre-analysis段階における検体の品質管理の留意点を把握し、適切な病理検体を遺伝子パネル検査用に提出することができる。
2. 遺伝子パネル検査の特徴を説明できる。
3. 遺伝子パネル検査にかかわる遺伝学的及び分子生物学的用語が理解できる。
4. 遺伝子パネル検査の同意説明時に、遺伝子パネルのメリット・デメリットについて適切に説明ができる。
5. エキスパートパネルに参加し、主治医としての役割を果たし協同することができる。
6. エキスパートパネルのレポートの内容を理解、説明できる。
7. エキスパートパネルのレポートに基づき、結果を患者に簡潔に説明できる。
8. エキスパートパネルのレポートに基づき生じる問題について多職種との連携を含めた問題解決能力を発揮できる。
9. 遺伝子異常のエビデンスレベルについて概略を説明できる。
10. がんゲノム医療に関するガイダンス等の指針について説明することができる。
11. 意思決定支援を行うための患者申出療養、治験について説明できる。
12. 生殖細胞系列変異と体細胞変異の違いを説明できる。
13. 二次的所見に関して説明し、次のとるべきアクションを説明できる。
14. 遺伝子パネル検査の説明に必要な薬物療法等に関わる知識として、対象がん種の診療ガイドラインを理解する。
15. C-CATレポートを参照することができる。
講習会 開催済み;2021年10月9日(土)
講習会プログラム内の事例検討でいただきました質問について、回答いたしますのでご参照ください。
<いただいたご質問に対する回答※>
事例検討③45歳・進行胃癌で、FoundationOne CDx panelにてBRCA2変異(S1882*)検出された症例に対する対応方針として、回答は③(開示対象であり、ご本人に遺伝カウンセリング受診を進める)で良いかと思いますが、その後の対応でご希望あれば保険でのBRCA解析と共に自費診療のシングルサイト解析もありそうでしょうか?
→ ご指摘の通りで、患者様ご本人(III-2)が遺伝カウンセリングを施行の上、ご希望された場合には、現時点では自由診療でのシングルサイトの提供となるかと思います。
またほかの方のご質問にもありますが、胃癌発症者に対するMyriad BRACAnalysisの提供は保険適応外になります。
T-only CGPでBRCA1/2が検出され、PARP阻害薬が推奨になる場合、胃がんであってもHBOC診療の手引き2017にある「がん発症者でPARP阻害薬に対するコンパニオン診断の適格基準を満たす場合腫瘍組織プロファイリング検査で、BRCA1または/かつBRCA2の生殖細胞系列の病的バリアント保持が疑われる」によりBRACAnalysisの適応になるという解釈の可能性はないでしょうか?
→ ご質問ありがとうございます。
ご指摘のようにHBOC診療の手引き2017には、そのように記載はありますが、2020年の診療報酬改定における厚生労働省の資料にはあくまでも、遺伝性乳癌卵巣癌症候群の症状である乳癌や卵巣・卵管・腹膜癌を発症している患者様が前提となる記載がありますので、他癌種の発症者に対するMyriad BRACAnalysisの提供は保険適応外になります。
がん遺伝子パネル検査後の結果説明時、遺伝カウンセリング加算はとれるのでしょうか?
→ “遺伝カウンセリング加算”は、あくまでも区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査、区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査又は遺伝性腫瘍に関する検査( 区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。)を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合に算定できますので、がん遺伝子パネル検査の結果説明の際は、“遺伝カウンセリング加算”は算定できません。
ただし、がんゲノム中核拠点病院・拠点病院・連携病院において、がんゲノムプロファイリング検査を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、“遺伝性腫瘍カウンセリング加算”として算定することが可能です。
事例検討症例のように実際にご本人がシングルサイトの検査を希望され、変異が陽性であったと仮定した場合、その後に叔母も遺伝学的検査を希望された場合にシングルサイト or BRACAnalysisのどちらの検査をお勧めされますか?
→ 自由診療でかかる費用と保険診療でかかる費用の違い、その方の現在の病状、また実父の遺伝学的検査の有無など様々な観点を考慮する必要があります。
叔母さまは45歳乳癌発症であり、HBOC診療の手引き2017にもある“45歳以下の乳癌発症”が該当することなどを考慮すると、保険診療でのMyriad BRACAnalysisが提供可能となりますが、混合診療になる可能性がない場合においては、自由診療でのシングルサイト検査のほうが、患者様の費用負担軽減につながることから、選択肢としても十分あり得るかと思います。
BRCAなど特定遺伝子の場合、VAF>10%のとき開示すべきとした根拠は?腫瘍含有率にもよると思いますが。
→ ご質問ありがとうございます。
ESMOからのガイドライン(文献 1, 2) に記載されているバリアントアレル頻度(VAF)を準拠しながらもVAFが低値でもgermlineが存在すること、またBRCA1、BRCA2などの遺伝子を他遺伝子と区別して扱っている理由の一つに、これら由来の疾患( 遺伝性乳癌卵巣癌症候群やリンチ症候群 )は、病的バリアント保持者に対する医学的管理・サーベイランスに関するエビデンスが充実していることの観点も考慮され、今回の小杉班のあらたな腫瘍細胞のみを対象としたがん遺伝子パネル検査における二次的所見の生殖細胞系列確認検査運用指針Ver2(文献 3) となっていると考えています。
文献
1. Germline-Focused Analysis of Tumour-Only Sequencing: Recommendations from the ESMOPrecision Medicine Working Group. Mandelker D, Donoghue MTA. Talukdar S, et al. Ann Oncol.30(8)1221–1231 (2019).
2. Erratum to ‘Germline-focussed analysis of tumour-only sequencing: recommendations from the ESMOPrecision Medicine Working Group’ Mandelker D, Donoghue MTA. Talukdar S, et al. Ann Oncol.32(8):1069-1061 (2021).
3. https://www.amed.go.jp/news/seika/kenkyu/20211020-01.html
germlineの開示を希望されていない患者に見つかった場合の対応について、どうされているか伺いたいです。当院で1例あった際には、継続フォローをして御本人の意向が開示希望に変わった段階で開示をして、確認検査に進みました。血縁者にプラスになる情報であり、開示の価値はもちろんありますが、御本人の知らない権利をどこまで担保するか難しい問題だと感じています。
→ ご指摘の通りで非常に難しい観点が含まれているかと思います。
患者様の意向も大切であるとともに、血縁者の方の意向、さらには患者様と血縁者がどのようにお話をされているのか、指摘された遺伝子のアクショナブルの程度など、考慮すべきことは多岐に及ぶかと思います。
BRCA1, BRCA2以外にもリンチ症候群のようなhighly-actionableな遺伝子に関しては、病的バリアント保持者に対する医学的管理・サーベイランスに関するエビデンスが充実しており、血縁者の方への臨床的有益性も考慮する必要があるため、まずはなぜご本人が知りたくないと考えているのか、そのあたりのプレカウンセリングを行うことも重要になるのではないかと考えますし、またご本人の理解の状況も確認する必要があるかと思います。
がん遺伝子パネル検査の際には臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラーも同席のうえで、まずはお話を聞いてみることから対応を始めるかと思いますし、健康管理に役立つ二次的所見の血縁者への伝達については、まず患者様本人から血縁者へ行うことが原則となりますが、患者の病状などによっては医療者から伝達することも必要となるかと思います。
状況によっては個人の判断ではなく、院内倫理委員会などで承認を得たうえで、血縁者への開示も検討する場合もあるかと思います。
※本回答内容は現時点(2021年10月)の内容であり、今後の状況等により変化します。




