〈下記の症状があればご紹介下さい。〉
頭痛、めまい、ふらつき、立ち眩み、ふるえ、脱力、けいれん、顔・手足の疼痛や感覚鈍麻、動作の不自由、歩行障害、眼瞼下垂、物忘れ、失神、意識障害など
(精神的な異常や心理的な障害などを中心とする場合は、当科の適応ではありません。)
○…初診・再診とも診療 □…初診のみ診察 △…再診(予約)のみ診察 ー…休診
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★は、ご紹介患者さまの予約枠があります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
脳神経内科一般 |
AM | ★坂田 花美 ★上田 昌美 ★寺山 敦之 |
★田港 朝也 ★三井 良之 ★山岸 裕子 |
★桑原 基 ★寒川 真 ★平野 牧人 |
★福本 雄太 ★西郷 和真 ★吉川 恵輔 |
★平野 牧人 ★西郷 和真 ★桑原 基 |
| PM | ★森田 顕 福本 雄太 ★道浦 徹 |
田港 朝也 ★金 蓮姫 |
★桑原 基 ★寒川 真 ★平野 牧人 永井 義隆 |
★寒川 真 三井 良之 ★藤井 佳奈子 永井 義隆 |
★吉川 恵輔 ★名村 仁志 ★稲田 莉乃 |
|
| 遺伝診療外来 | AM | 西郷 和真 | ||||
| PM | ||||||
| ボトックス外来 《13:00-》 |
AM | 平野 牧人/寒川 真 | ||||
| PM | 高田 和男 |
| 担当医師名 | 専門分野 | 専門医資格 |
|---|---|---|
 主任教授、診療部長
主任教授、診療部長永井 義隆 |
脳神経内科一般 | ― |
 臨床教授
臨床教授三井 良之 |
脳神経内科一般、神経内科 | 日本神経学会神経内科専門医、日本内科学会総合内科専門医 |
 臨床教授
臨床教授平野 牧人 |
脳神経内科一般、神経内科 | 日本神経学会神経内科専門医、日本内科学会総合内科専門医、臨床遺伝専門医制度委員会臨床遺伝専門医、日本脳卒中学会脳卒中専門医 |
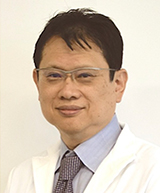 臨床教授/遺伝子診療部副部長
臨床教授/遺伝子診療部副部長西郷 和真 |
脳神経内科一般、遺伝診療、神経内科 | 日本内科学会総合内科専門医、臨床遺伝専門医・指導医、遺伝性腫瘍専門医、日本認知症学会認知症専門医、日本頭痛学会専門医 |
 講師
講師桑原 基 |
脳神経内科一般 | 日本神経学会神経内科専門医、日本内科学会総合内科専門医 |
 講師
講師寒川 真 |
脳神経内科一般 | 日本神経学会神経内科専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本認知症学会認知症専門医、日本頭痛学会頭痛専門医、日本臨床神経生理学会専門医 |
 医学部講師
医学部講師稲田 莉乃 |
脳神経内科一般 | 日本神経学会神経内科専門医、日本内科学会総合内科専門医 |
 医学部講師
医学部講師田港 朝也 |
脳神経内科一般 | 日本神経学会神経内科専門医 |
 医学部講師
医学部講師吉川 恵輔 |
脳神経内科一般 | 日本神経学会神経内科専門医 |
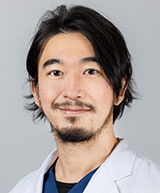 医学部講師
医学部講師福本 雄太 |
脳神経内科一般 | 日本神経学会神経内科専門医 |
 医学部助教A
医学部助教A坂田 花美 |
脳神経内科一般 | ― |
 医学部助教A
医学部助教A寺山 敦之 |
脳神経内科一般 | 日本神経学会神経内科専門医 |
 医学部助教A
医学部助教A名村 仁志 |
脳神経内科一般 | ― |
 医学部助教A
医学部助教A道浦 徹 |
脳神経内科一般 | 日本専門医機構認定内科専門医、日本神経学会神経内科専門医 |
 医学部助教A
医学部助教A久富 隆寛 |
脳神経内科一般 | 日本専門医機構認定内科専門医 |
 医学部助教A
医学部助教A平井 敦樹 |
脳神経内科一般 | ― |
 医学部助教B
医学部助教B中村 寛人 |
脳神経内科一般 | ― |
 医学部助教B
医学部助教B山本 眞紀子 |
脳神経内科一般 | ― |
 専攻医
専攻医山名 健介 |
脳神経内科一般 | ― |
 専攻医
専攻医星野 玄樹 |
脳神経内科一般 | ― |
 専攻医
専攻医渡部 瑛惠 |
― | ― |
 非常勤医師
非常勤医師宮本 勝一 |
脳神経内科一般 | 日本神経学会神経内科専門医、日本内科学会総合内科専門医 |
 非常勤医師
非常勤医師髙田 和男 |
ボトックス治療 | 日本神経学会神経内科専門医、日本内科学会総合内科専門医 |
 非常勤医師
非常勤医師上田 昌美 |
脳神経内科一般、リハビリテーション科、神経内科、神経筋疾患 | 日本神経学会神経内科専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医 |
 非常勤医師
非常勤医師山岸 裕子 |
脳神経内科一般 | 日本神経学会神経内科専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本臨床神経生理学会専門医 |
 非常勤医師
非常勤医師藤野 雄三 |
脳神経内科一般 | 日本神経学会神経内科専門医、日本内科学会総合内科専門医 |
 大学院生
大学院生藤井 佳奈子 |
脳神経内科一般 | 日本専門医機構認定内科専門医、日本神経学会神経内科専門医 |
専門の神経内科医による病歴の聞き取りおよび詳しい神経学的診察を行い、MRIなどの画像診断、筋電図などの電気生理学的検査、抗体や遺伝子検査などの生化学的検査の結果をふまえて診断していきます。その上で最新の知見に基づいた適切な治療を行います。
また日常生活指導を行って、QOLを高めるよう指導します。
入院症例については、毎週医局員全員が揃う症例検討会で検討のうえ、診療方針を決定しています。