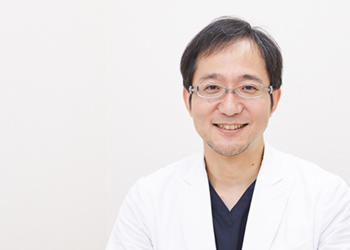
特命准教授
川上尚人
未来を拓く気概をもつ若い先生方へ
近畿大学医学部腫瘍内科
主任教授 林秀敏

大学生時代の私は、部活の先輩の「今勉強したら、医者になってから勉強する楽しみがなくなるで」という一言を頼りに部活動や遊びに明け暮れておりました。
何とか卒業して国家試験合格を果たし、住友病院総合診療科で初期研修を行う機会をいただきましたが、先輩の一言は医師になってから一心不乱に勉強する、そして勉強を楽しめるきっかけになったように今は感じられます。
当時、住友病院では研修医ながら内科外来を担当することができ、患者さんを診て鑑別診断を挙げ、診療していくという内科的なトレーニングを受けることができました。40代50代の指導医の先生方はもとより、1学年上、2学年上の若い先生方から内科医としてのありかたを実践的に学ばせていただき、たいへん貴重な経験だったと感謝しています。

印象深い患者さんは幾人もおられるのですが、なかでも発作性夜間血色素尿症(PNH)を発見できた患者さんのことは鮮明に記憶しています。血尿を主訴として受診された方で、当初は腎臓の病気が疑われ、腎臓内科の先生のもとでいろいろ調べたのですが、考察の結果、鑑別診断の1つとしてPNHを挙げることができました。
確定診断には「シュガー・ウォーター・テスト」が用いられるのですが、これはたいへん手間のかかる検査であり、オーダーした検査部からは難色を示されました。いろいろと証拠をお示しして検査していただいた結果、陽性所見が得られてPNHであることが判明しました。
実は当時、内科を志望していたわけではなかったのですが、上級医である血液内科の先生に「林君は内科向きやね」とおっしゃっていただいたことが自分の将来を変えたといえるかもしれません。
呼吸器内科の研修中に半年以上担当した進行肺がんの患者さんには、診断から化学療法、そして永眠されるまで、毎日ベッドサイドでいろいろな話をうかがい、ときに研修医としての至らなさからお叱りを受けもしました。この患者さんには、ある意味で主治医として以上のご信頼をいただき、最期の瞬間には手を握りながらお別れと感謝の言葉をいただきました。その当時の未熟な自分にも心に残る、そしてがん診療の道を進むきっかけとなった患者さんでした。
住友病院で過ごした3年間は、呼吸器内科、血液内科、神経内科、腎臓内科、内分泌代謝内科などローテートしたすべての診療科での研修が楽しく、もっともっと幅広い疾患を診たいという思いが募りました。当時、臓器横断的な診療を行っている医療機関を知らなかったことから、後期研修では専門的研修のみならず救急診療や集中治療など臓器横断的なさまざまな経験を積みたいという思いから倉敷中央病院呼吸器内科にお世話になることにしました。
結果的に多くの肺がんの患者さんを診療する機会をいただき、診断から治療、緩和ケアまでトータルに経験することができました。もう1つ大きかったのは、分子標的治療薬が開発された時期であり、当時としては劇的な有効性を示していたことから、臨床研究の面白さに気づく契機となったことです。
倉敷中央病院呼吸器内科は、がん患者さんを対象に多施設共同研究を実施する西日本がん研究機構(WJOG)に属しており、私自身、さまざまな臨床試験に携わる機会に恵まれました。
そんな折に近畿大学腫瘍内科の主任教授でいらした中川和彦先生、准教授でいらした岡本勇先生(現・九州大学医学研究院臨床医学部門呼吸器内科学講座教授)といった先生方の知己を得て、近畿大学腫瘍内科という臓器横断的ながん診療を行う医局があることを初めて知りました。
中川先生がおっしゃったのは、「私はまだ真の腫瘍内科医ではない」ということです。中川先生に「私は肺がんだけをやってきた人間であり、林先生のような若い先生方に真の腫瘍内科医になって欲しい」というお言葉をかけていただいたことがきっかけで、近畿大学腫瘍内科に入局したいと強く望むようになりました。

こうしたご縁から、私は2009年4月に近畿大学腫瘍内科に入局し、同学年で近畿大学出身の先生がさまざまながん患者さんに対してスマートに診療している姿に刺激を受けながら、腫瘍内科医としての経験を積みました。
その一方で、ご指導いただいた先生のお1人であった岡本先生より肺がんに対する臨床試験のメタ解析、システマティックレビューのアイデアをご提案頂き、統計家の先生にもご指導をいただいてまとめた論文がANNALS OF ONCOLOGYに掲載され、このことが博士号取得につながりました。
腫瘍内科では、当時から分子標的治療薬の耐性因子を検討する研究などが盛んであり、私も基礎研究に参加するよう強くお声をかけていただいていました。しかし、その時点では腫瘍内科医として臨床面で一人前になりたいという気持ちが強く、「基礎研究にはまったく興味がありません」と公言していました(笑)。基礎研究というとマウスを用いて研究するのが一般的なイメージだと思いますが、実は私もそう考えていたのです。
しかし、本学の西尾和人先生が主宰されるゲノム生物学教室では、患者さんの臨床検体から得られた遺伝子情報と臨床情報を融合させ、新規のがん遺伝子の発見や治療法の開発に結び付けようという、当時としては先駆的な研究をしていました。
私もこうしたトランスレーショナルリサーチに興味を惹かれ、2年間、この教室に研究学内留学しました。これを契機にトランスレーショナルリサーチや胃がん細胞株を利用した基礎研究を行うことができ、自らのリサーチマインドの幅が大きく広がったと感じています。
同教室在籍2年目には、、住友病院での初期研修の3年後輩で、現在は腫瘍免疫の世界でご高名な冨樫庸介先生(現岡山大学学術研究院医歯薬学域腫瘍微小環境学教授)が大学院生として入局され、細胞株を片手にいろいろな研究内外のよもやま話をしながら、さらにアイデアや知識を深め、腫瘍学の将来展望を議論することができたことはよい思い出です。
ゲノム生物学教室での研究学内留学後、中川先生のおはからいで岸和田市民病院に腫瘍内科部長として赴任することになりました。当時、岸和田市民病院の腫瘍内科は発足から数年で未成熟な状況でしたが、むしろそれが幸いし、外科医である小切匡史病院長のサポートのもと、近畿大学腫瘍内科に在籍されていた文田壮一先生(現近畿大学奈良病院)や岡本邦男先生(現香川県立中央病院部長)とともに市中病院における腫瘍内科のあるべき姿を追求することができました。
小切先生は、「外科医が化学療法を行う時代はすでに終わっており、腫瘍内科主導で化学療法をどんどん進めていってほしい」とおっしゃってくださいました。また、耳鼻科部長の梶川泰先生からは腫瘍内科がリードし、外科、放射線治療、内科によるチーム診療を進められるよう、大きなサポートをいただきました。
私たちはこうした先生方のお力添えを得て、腫瘍内科医が化学療法を行う疾患を肺がん、消化器がんから頭頸部がん、口腔がんへと広げていきました。岸和田市民病院での2年間は、市中病院においてさまざまな臓器専門科と連携しながら臓器横断的な診療を担う腫瘍内科の役割を実感できた、とても有意義な時期だったと考えています。
2015年4月に近畿大学腫瘍内科に戻りましたが、その直前、中川先生からのちにノーベル生理学・医学賞を受賞される京都大学の本庶佑先生に招かれているので同行するようご指示があり、ご一緒にうかがいました。
中川先生は2014年の日本肺癌学会学術集会を主宰され、本庶先生に特別講演を依頼されていたことから交流があったということです。その際、本庶先生より免疫チェックポイント阻害薬において当時まだ知見が乏しかったバイオマーカーについて、臨床検体を扱った研究に長い歴史のある近畿大学究/トランスレーショナルリサーチを共同で行うことをご提案いただき、医師主導治験であるNivolution試験を行うことができました。
このことは、1つにはアンメットメディカルニーズに対する医師主導治験の遂行と近畿大学における体制整備のお手伝いをし、その当時はまだ黎明期であった腫瘍免疫に関するトランスレーショナルリサーチについて世界最高峰の教室の見識をお示しいただいたという意味において、私にとってたいへん大きな出来事でした。
本庶研の先生方と医師主導試験を行うためのプロトコールについて、半年にわたって連日夜遅くまで討議を重ねたことも忘れがたい思い出です。
当時、私にとっては原発不明がんついての治療成績の向上も重要なミッションでした。原発不明がんとは、原発巣がわからないまま転移巣のみにがんが存在するという特殊な希少がんであり、その治療はきわめて困難であることが知られていました。
中川先生が主任研究者を務められた厚生労働省中川班では、すでに患者さんのがんの遺伝子情報からその原発不明がんの由来、つまりは隠れた原発巣がどこであるかを推定し、治療方針を決めるための臨床研究を行っていたのです。
当初、この臨床研究は当科の倉田宝保先生(現・関西医科大学呼吸器内科学教授)が主導され、ゲノム生物学教室が協力して実施していたのですが、倉田先生が関西医科大学に栄転されたあとに私が引き継いで完遂し、論文化することができました。
その後、次世代シークエンサーが幅広く使えるようになり、がんの遺伝子異常や遺伝子発現からの原発巣推定から原発不明がんの治療方針を決めるための多施設共同研究が腫瘍内科を有する全国各地の医療機関の協力のもとで完遂し、こちらも論文化できたことはたいへん貴重な経験でした。
こうした経験と免疫チェックポイント阻害薬における医師主導治験の経験が、原発不明がんに対するニボルマブの適用拡大を目指したNivoCUP試験の完遂に結びつきました。この試験は、われわれの熱意に賛同していただいた小野薬品工業のご支援のもと、当科の谷崎潤子先生が研究事務局として試験の遂行を牽引して行われました。
最終的にはニボルマブの適用拡大につながり、原発不明がん患者さんに対して免疫チェックポイント阻害薬使用の機会をもたらすことができました。この研究成果はネットニュースで報道され、患者さんから多数のお問い合わせのお電話をちょうだいしたのが印象的でした。
免疫チェックポイント阻害薬はまさしく臓器横断的な治療手段であり、当科でも肺がん、消化器がん、乳がん、頭頸部がん、原発不明かんなど幅広いがん種に対して1,000人以上の患者さんに使用されています。もちろん完璧な治療ではなく、有効性を示すのは一部の患者さんにとどまりますが、患者さんには薬物治療を行いながらであっても元気に人生をまっとうできるチャンスが生まれ、また腫瘍内科医による臓器横断的な治療の重要性を深く認識する機会となったと考えています。
一方、免疫チェックポイント阻害薬には「免疫関連有害事象」と呼ばれる副作用があり、さまざまな臓器に腸炎、肺炎、脳炎などの有害事象をもたらすことがあります。
免疫関連有害事象に対しては、腫瘍内科医の診断がきわめて重要であり、できるかぎり早く見つけて早く治療に持ち込むというマインドが求められます。その意味において、初期研修で内科的な診断学を実践的に学ぶことができたことは、たいへん有益だったと考えています。
主任教授を拝命するにあたり、最大の課題として肝に銘じているのは、より多くの優れた腫瘍内科医を育成し、輩出することです。最近では臓器横断的に診療を行う腫瘍内科の重要性が広く認識され、全国各地の医療機関から「腫瘍内科をつくりたい」「腫瘍内科医を派遣してほしい」といったご要望が数多く寄せられています。
こうした医療機関の期待にお応えし、日本のがん診療のレベルを向上しうる腫瘍内科医を育成するため、より一層、教育面の充実を図りたいと考えています。
初期研修に臨む1年目、2年目の若い先生方に対しては、数多ある抗がん剤の選択や投与方法などを覚えることも大事かもしれませんが、まずは内科医として必要な幅広い疾患について知識を深め、経験を積んでいただきたいと思っています。感染症や糖尿病などの身近な疾患に対し、どのように診断、治療を進めていくか、そして実際に患者さんとどのように接してともに意思決定を図っていくかを実践的に学んでいただきたいと考えています。
3年目以降の後期研修で腫瘍内科に入局された場合、専攻医として比較的早い段階から徐々に外来診療を開始し、抗がん剤の選択、投与方法、副作用対策といった腫瘍内科医としての専門事項に理解を深め、5年目が終了するまでには、1人である程度ディシジョンできるような腫瘍内科医に育っていただけたらと考えています。
教育体制として、最近では1年目の先生を2年目の先生が教え、2年目の先生を専攻医の先生が教えることで自身も学ぶといった、「屋根瓦方式」を採用しています。後輩を教えることで、自らの知識も定着させることができるように感じております。
もう1つの課題は研究面の充実です。現在、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬をめぐる研究は国際的にすさまじいスピードで進んでおり、1つの臨床教室が立ち向かうのはたいへん難しくなっている状況です。
しかしながら、実際に患者さんを診る腫瘍内科の立場からクリニカルクエスチョンを探り、患者さんやご家族の幸福に還元できるような研究に、いろいろな研究室とも共同することで努めていきたいと思っています。
診療面においては、当然のことながらどのようながん患者さんであってもお断りすることなく、診療から緩和ケアにいたるまで最善を尽くす必要があります。誰しも寿命があり、与えられた寿命のなかで可能な限り元気に幸せに暮らしていけるような診療に努めていきたいと考えています。
私はもともと身内に医師がいない家庭環境で生まれ育ちましたが、医師を志した遠因には6歳のときに父を肝臓がんで亡くしたことが関わっているかもしれません。父が何か月にもおよぶ長期入院の合間、数日間だけ帰宅したときの様子などをおぼろげながら覚えており、その際のビデオテープも残っています。
父を亡くしたことは、私自身が医師として患者さんとご家族の気持ちに寄り添う上で大きな経験となっています。父の死後、家族一同大きな悲しみに暮れましたが、家族1人ひとりはその後もそれぞれの人生を歩みますし、私自身、父が遺したものを生かしてここまで歩んできたと思っています。
がん患者さんを診療する上で元気に長生きできるよう全力を尽くすことは当然ですが、限りある寿命のなかで患者さん自身がどう過ごされたいのか、ご家族に何を遺されたいのかを意識しながら診療していきたいと念じています。
また、医師の働き方改革が重要視される昨今、医師が自らの心身の健康に留意し、ワークライフバランスを整えていけるような取り組みも重要です。当科では、以前から入院患者さんに対しては主治医1人で担当するのではなく、主治医の治療方針をチームで共有し、協力し合って診療に当たるようにしています。
現状でも、当直明けは帰宅する、出産や育児など必要に応じて休暇や時短勤務が選択できる、臨床や研究に特化して専門性を追求できる、留学希望に応えられるといった、1人ひとりのご希望に沿った勤務体制がとれるのが当科の特徴ですが、さらに働きやすい環境づくりに努めていきたいと思っています。

以前、私は近畿大学腫瘍内科について、多彩なサブスペシャリティ、特徴を有する腫瘍内科医が集い、ともにフロンティアを目指す合衆国と表現したことがあります。こうした医局をつくられた中川先生は、先述のように「私はまだ真の腫瘍内科医ではない」とおっしゃり、次代を担う若い世代にバトンを託されました。
他施設の先生方から「どのような医師に入局してほしいか」といったご質問をいただくのですが、私の答えも中川先生と同じです。腫瘍内科に興味を抱く先生であれば、どのようなキャリアやスキル、志向をお持ちの方でも、ご一緒に「真の腫瘍内科医」を目指して未来を切り開いていただければ幸いです。